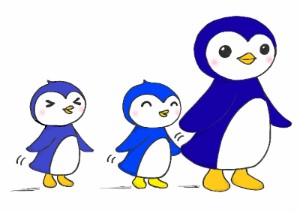ORCAレセコンをご利用中のお客様
ORCAレセコンをご利用中のお客様
Q:
ログイン画面にてユーザ名、パスワードを入力しても、「パスワードが違います。もう一度試してください。」と表示され、ログインできません。
A:
ユーザ名の入力時に大文字になっていませんか? または、キーボードの「Caps Lock」のライトが光っていませんか? その場合は、キャピタルロックがONになっています。
Shiftキーを押しながら、Caps Lockを1回押してキャピタルロックを解除してから、再度入力してください。(ライトが光っていなければ解除されています。)
Q:
65歳から75歳未満で後期高齢者医療の保険証を持っておられる患者さんが限度額適用認定証を提示された場合、公費欄や所得者情報の登録はどのようにすればいいですか?
A:
この場合、65~69歳でも70歳以上の限度額適用認定証を持っていると思われます。
提示された限度額適用認定証の適用区分に従い、入力してください。
限度額適用認定証の入力方法は、以下のリンク先を参照にしてください。
高額療養費制度見直しにともなう患者登録入力方法について(H30.8改定)
投稿日時: 2018.06.29 カテゴリ: 保険・公費
Q:
Ubuntu16.04 1280×1024のモニタで1024×768の解像度にできません。この解像度に調整しても、再起動すると元に戻ります。
A:
自動起動するアプリケーションに以下を追加する。
xrandr -s 1024×768
投稿日時: 2018.06.20
Q:
セット登録をしている検査項目の一部がH30年度の診療報酬改定で削除された(例:ZTT)ので、セットの編集をするためセット登録の画面にて内容を展開したところ、ZTTの記載がありませんでした。
そのまま「F12 登録」をクリックすると「マスタが存在しません」とエラーメッセージがでてきます。
A:
H30年4月以降にセット登録の編集をすると、H30年3月31日で削除されたZTTのマスタコード自体が存在しないため、ZTTが書かれていた部分は空白となり、エラーメッセージが表示されます。
環境設定にてH30年3月以前の日付に設定してから編集作業を行ってください。
Q:
IOが遅いHDDにPostgreSQLのrestoreを行うと異常に遅い。1GBあたり10時間以上かかっている。
A:
restoreの時だけ、postgresql.confの「#fsync = on」を「fsync = off」にしてください。
restoreが終われば元に戻してください。
投稿日時: 2018.04.24 カテゴリ: Linux・Ubuntu・Debian
Q:
A群β溶連菌迅速試験定性、マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)に鼻腔・咽頭拭い液採取(5点、H28改定で新設)は算定できるか。
A:
D012感染症免疫学的検査の「20 A群β溶連菌迅速試験定性」「25インフルエンザ抗原定性」「24 RSウイルス抗原定性」「26 マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)」「35 アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」など、D017細菌顕微鏡検査、D018細菌培養同定検査、D023微生物核酸同定・定量検査などの実施にあたり、鼻腔・咽頭拭い液を採取した場合、1日につき1回算定できます。
投稿日時: 2018.04.18 カテゴリ: 診療行為入力
A:
オンライン診療に関する項目を引用しました。
A003 オンライン診療料
(1)オンライン診療料は、対面診療の原則のもとで、対面診療と、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察(以下「オンライン診察」という。)を組み合わせた診療計画を作成し、当該計画に基づいて計画的なオンライン診察を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定できる。なお、当該診療計画に基づかない他の傷病に対する診察は、対面診療で行うことが原則であり、オンライン診療料は算定できない。
(2)オンライン診察は、(1)の計画に基づき、対面診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理のもとで実施されるものであり、連続する3月の間に対面診療が1度も行われない場合は、算定することはできない。ただし、対面診療とオンライン診察を同月に行った場合は、オンライン診療料は算定できない。
(3)オンライン診療料が算定可能な患者は、区分番号「B000」特定疾患療養管理料、「B001」の「5」小児科療養指導料、「B001」の「6」てんかん指導料、「B001」の「7」難病外来指導管理料、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-10」認知症地域包括診療料、「B001-3」生活習慣病管理料、「C002」在宅時医学総合管理料又は「I016」精神科在宅患者支援管理料(以下「オンライン診療料対象管理料等」という。)の算定対象となる患者で、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過し、かつ当該管理料等を初めて算定した月から6月の間、オンライン診察を行う医師と同一の医師により、毎月対面診療を行っている患者に限る。ただし、オンライン診療料対象管理料等を初めて算定した月から6月以上経過している場合は、直近12月以内に6回以上、同一医師と対面診療を行っていればよい。
(4)患者の同意を得た上で、対面による診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画(対面による診療の間隔は3月以内のものに限る。)を作成する。また、当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。
(5)当該計画に沿った計画的なオンライン診察を行った際には、当該診察の内容、診察を行った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。
(6)オンライン診察を行う医師は、オンライン診療料対象管理料等を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。
(7)オンライン診察を行う際には、厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う。
(8)オンライン診察は、当該保険医療機関内において行う。
(9)オンライン診療料を算定した同一月に、第2章第1部の各区分(通則は除く。)に規定する医学管理等は算定できない。
(10)オンライン診察時に、投薬の必要性を認めた場合は、区分番号「F100」処方料又は区分番号「F400」処方箋料を別に算定できる。
(11)当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
(12)当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。
(13)オンライン診療料を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、該当するオンライン診療料対象管理料等の名称及び算定を開始した年月を記載すること。
1 オンライン診療料に関する施設基準
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。(ただし、区分番号「B001」の「5」小児科療養指導料、区分番号「B001」の「6」てんかん指導料又は区分番号「B001」の「7」難病外来指導管理料の対象となる患者は除く。)
(3) 当該保険医療機関において、1月当たりの区分番号「A001」再診料(注9による場合は除く。)、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「A003」オンライン診療料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定回数に占める区分番号「A003」オンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であること。
疑義解釈その1、オンライン請求に係る抜粋
問 10 区分番号「A003」オンライン診療料を算定する患者にオンライン診療を行う際に、オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患について診療を行うことは可能か。
(答)オンライン診療の診療計画に含まれていない疾患については、対面診療が必要である。
問 14 オンライン診察を行うにあたり、情報通信機器を医療機関に設置した上で、医師の自宅などへ画像情報等を転送し、オンライン診察を行う場合も算定可能か。
(答)不可。オンライン診察を行う医師は、当該医師が所属する保険医療機関においてオンライン診察を行う必要がある。
問 17 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、当該保険医療機関において、オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要か。
(答)オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要である。
問 20 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準において、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、離島・へき地においても、当該施設基準を満たす必要があるか。
(答)離島・へき地においても、オンライン診療料等を算定する場合は、原則として、当該施設基準を満たす必要がある。ただし、離島・へき地において緊急時も当該医療機関が対応することとなっている場合は、30分を超える場合であっても、施設基準を満たすものとして取扱って差し支えない。
問 21 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準について、既に主治医として継続的に診療している患者であって、状態が安定している患者についても、「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」という要件を満たす必要があるのか。
(答)満たす必要がある。ただし、平成30年3月31日時点で、3月以上継続して定期的に電話、テレビ画像等による再診料を算定している患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、オンラインで診察を行った場合にも、電話等による再診として再診料を算定して差し支えない。
問 22 区分番号「A003」オンライン診療料に係る施設基準にある「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関で対面診療が可能な体制」とは、夜間や休日など当該医療機関で対応できない時間帯について、あらかじめ救急病院などを文書等で案内することでもよいか。夜間や休日も当該保険医療機関で対応が必要か。
(答)夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね30分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要である。
(7) 電話等による再診
ア 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から直接又は間接(電話、テレビ画像等による場合を含む。)に、治療上の意見を求められた場合に、必要な指示をしたときには、再診料を算定できる。なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない。ただし、平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、当該再診料を引き続き算定することができる。その場合には、オの規定にかかわらず、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算は算定できない。
イ 電話、テレビ画像等を通した再診(聴覚障害者以外の患者に係る再診については、ファクシミリ又は電子メール等によるものは含まない。)については、患者の病状の変化に応じ療養について医師の指示を受ける必要のある場合であって、当該患者又はその看護に当たっている者からの医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合に限り算定する。ただし、電話、テレビ画像等を通した指示等が、同一日における初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容のものである場合等には、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定できるものとし、この場合においては、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該ファクシミリ等の写しを貼付すること。
ウ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、「注4」の乳幼児加算を算定する。
エ 妊婦又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、「注15」の妊婦加算を算定する。
オ 時間外加算を算定すべき時間、休日、深夜又は夜間・早朝等に患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示した場合は、時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・早朝等加算を算定する。ただし、ファクシミリ又は電子メール等による再診については、これらの加算は算定できない。
カ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。
キ 当該再診料を算定する際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
投稿日時: 2018.04.14 カテゴリ: 診療報酬改定
A:
「12 登録」の「特記事項・レセプト分割」タブで「09 施」を設定します。
または「21 診療行為」で「099990109 特記事項09 施」を入力します。
初診料、再診料は算定できないため「初診料(DUMMY)」などが自動算定されます。
レセプトには、初診料(DUMMY)および再診料(DUMMY)の合計回数「【配】○○回」を自動記載します。
投稿日時: 2018.04.14 カテゴリ: レセプト作成
Q:
1年間の医療費の総額を1枚の領収書や証明書等で発行できますか?
(例:平成29年1月1日~平成29年12月31日分)
A:
「支払証明書」で発行できます。
1.「23 収納」→患者番号入力
2.「Shift+F10 支払証明」
3.支払証明書・・・右▼ ボタンをクリックし、「2 月別証明書」を選択
4.入外区分・・・右▼ ボタンをクリックし、「0 全て」を選択、又は「1 入院」「2 外来」から
発行したい区分のどちらかを選択
5.期間指定・・・右▼ ボタンをクリックし、「2 年」を選択後、右側に対象年(例:H29)を
入力し、ENTER
6.すぐに印刷する場合・・・「F12 印刷」をクリックし発行
プレビュー画面で確認してから発行する場合・・・「F10 プレビュー」をクリックし、
正常に処理されてから「F12 プレビュー」をクリックし、画面にて内容を確認後、
「F12 印刷」をクリックし発行
*「期間区分」~「自費内訳明細書」欄については、基本的には表示のまま設定変更する必要はありませんが、必要に応じて設定変更してください。
投稿日時: 2018.04.11
Q:
カルテ1号用紙を印刷したところ、スカイ・エス・エイッチ、カスタマイズカルテ1号用紙右上の負担割合が「0割」の表示になるのはなぜですか?負担割合は0割の患者ではありません。
A:
保険者番号も表示されていないのではないでしょうか。
「12 登録」画面にて保険組合せを選択せずに印刷した場合、印刷したカルテ1号用紙の保険者番号欄に保険者番号等が記載されないため「0割」と表示されます。
「12 登録」画面の右側「番号 保険組合せ」欄にて、印刷したい保険組合せをクリックして選択後、「F12 登録」をクリックしてください。
新規患者は「12 登録」画面で保険者番号等を入力後、「F5 保険組合せ」をクリックし、画面右側「番号 保険組合せ」欄に保険組合せを表示させ、印刷したい保険組合せをクリックして選択後、「F12 登録」をクリックしてください。